過去問1冊分のアウトプットができれば合格できる
試験で点を取るためには、アウトプットが必要です。
アウトプットとは、実際に問題を解くこと、自分の頭から知識をひっぱりだすことです。
結論としては、宅建士試験では過去問一冊分のアウトプットで合格点が取れます。
過去問以上に知識を広げると合格率が下がる
次のうち、どちらの方が合格する確率が高いと思いますか?
A 過去問1冊を勉強している人
B 過去問3冊+模擬試験3回分+予備校のテキストを勉強している人
合格ができない人、合格まで何年もかかってしまう人はBと考えます。
多くの教材に手を出せば出すほど、幅広い知識が身につくと考えてしまいます。
そして教材の消化不良を起こして知識が身につかず、不合格になるか、合格に数年かかって、「過去問だけで合格できる時代はおわった」「過去問以外の知識も勉強しないといけない」と間違えた結論を持つことになります。
教材は、1回目より2回目、3回目の方が早く読めます。
多くの教材に手を出すということは、一回目のスピードで読む機会が増えるということです。
例えば、5冊の教材を1回ずつ読む時間があれば、1冊の教材に絞れば20回以上読むことができます。
自分の机だけそうじするのと、自分の机を含めて会社全部の机をそうじする場合、自分の机がキレイになるのはどちらですか?
過去問を極めるのは楽じゃない
過去問だけで合格できると聞くと、「そんな簡単に合格できる試験じゃない」「過去問だけで合格できる時代は終わった」と言う人がいます。
この言葉の裏には、「過去問を極めることが簡単である」という認識があります。
過去問を極めることは非常に難しいことです。
過去問を極めるとは、「過去問を三周しましょう」というようなヌルい理解度ではありません。
過去問を選択肢ひとつひとつを、根拠をもって正誤の判断ができるようになること。
これが、過去問を極めた状態といえます。
この状態になるまでには、三周程度ではまったく足りません。
問題によっては30回、40回以上くりかえす必要が出てきます。
ここまでやって、ようやく合格点が取れるようになります。
さまざまな教材に手を出しながら過去問を数十回もくりかえすことはそもそも物理的に不可能です。
正しい勉強法をやっていた場合、複数の教材に手を出している時間がないことは明白です。
過去問+解説系教材がおすすめ
合格に必要なアウトプットの量は過去問一冊分です。
過去問一冊で完璧にアウトプットができれば、理屈上はそれだけで合格ラインを超えることが出来ます。
しかし、過去問だけで全ての勉強を完結できる人は、宅建士以外の法律系資格を勉強したことがある人でなければ難しいです。
そこで、インプット教材として解説系教材を用意することをオススメします。
時間がない社会人には、動画系教材がとくにオススメです。
【過去問の選びかた】どんな過去問でも良いわけじゃない
過去問には、大きく分けて三つの種類があります。
・分野別
・肢別
・年度別
それぞれ特徴があり、役割があります。
結論としては、極めるべき過去問題集は分野別のものです。
以下、それぞれの特徴を解説します。
分野別(オススメ)
分野別に過去問題がそのまま掲載されている問題集。
出題頻度や重要度で問題がピックアップされているので、ムダな勉強を省きつつ、特定の分野に集中して学習することができます。
選択肢レベルでは難問、悪問が含まれるため、学習効率は肢別問題集には劣るものの、本番の形式が崩れておらず、無意識に本番の形式に慣れることができます。
学習の中心に置く過去問題集としては一番オススメです。
肢別(時間が無く、一発逆転したいとき)
選択肢ひとつひとつを独立の問題としてまとめられた過去問題集。
選択肢レベルで問題が厳選されていて、難問、悪門がカットされています。
ムダな知識を覚える必要がないので、知識の習得だけでいうと非常に効率が良い。
そのかわり、本番の形式からかけ離れていて、試験の形式には慣れることができません。
他の法律系資格の取得者でかつ、本番まで時間がなく、一発逆転をねらうときに選択するとよいです。
年度別(直前期にオススメ)
年度ごとに問題が収録された問題集。
その年に出題された問題がすべて収録されている性質上、悪門、難問も含んでいる。
普段づかいするには学習効率は非常に悪い。
本番の形式に慣れるため、試験直前に取り組むのに向いています。
回答、解説が見開きになっているものがベスト
一番オススメの過去問題集は、見開きページの左に問題、右に回答が載っている分野別過去問題集です。
左ページで問題を読み、右で解説を見るという目線の動きだけで学習ができます。
カバンの中に過去問題集を入れておき、信号待ちをしている時間、電車に乗っている時間などのちょっとしたスキマ時間に学習ができるようになります。
回答、解説が別冊になっているタイプは、机がなければ勉強できず、学習がしにくくなります。
学習のしにくさは挫折率を高める原因になるので、選ばないようにしましょう。
試験に落ちた場合、過去問題集は買い替えるべきか
残念ながら試験に不合格になった場合、今年つかっていた過去問題集は1年古くなります。
新たに過去問題集を買おうか迷うところですが、1年程度であれば古くなっても試験の傾向を外していないのでそのまま使い続けても大丈夫です。
法改正にはどうやって対応すべきか
法改正を絡めた問題が出題された場合、過去問題集中心の学習では対応できません。
過去問演習で対応できない問題は、合否に関係がないので捨ててかまいません。
受検者の中では、過去問以上の学習をしていて、未知の問題にも対応できる人がいるかもしれません。
未知の問題に対応できてしまう人は、効率的に宅建士試験の学習ができていない人なので、全体の点数ではそうゆう人には勝てることになります。
まとめ
過去問題集一冊の知識をアウトプットできるようになることを目標にしてください。
初学者、独学者はインプット教材をひとつ用意することで教材の量としてはじゅうぶんです。
そして過去問題集は、なんとなく選んではいけません。
まずは左ページに問題、右ページに回答、解説が見開きになっている分野別過去問題集を入手しましょう。
あとは予定を立てて、正しい方法で努力を続けるだけです。

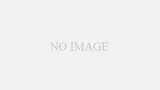
コメント