さあ!勉強するぞ!
と意気込んで、1ページ目から読み進めようと思っているそこのあなた、ちょっと待った!
学習する順番を工夫するだけで学習効率が変わってきます。
最終的にすべての科目を学習するからといって、1ページ目から真面目に取り組んでも効果的な学習とはいえません。
最初から手をつけるべき科目、直前期に仕上げた方が良い科目があるので、1ページ目から学習してくのは得策ではありません。
今回の記事では、効果的なスケジュールの立てかたをご紹介します。
スケジュールの立て方
科目ごとの得点のしやすさ、しにくさからスケジュールを立てていきます。
全体の計画としては、以下の順番で着手するのが効率的です。
- 民法
- 宅建業法
- 法令上の制限
- その他
学習の初期から着手することで、スケジュールの調整を何度もできるようにしておきます。
学習スケジュールの立てかたはこちらの記事
民法は初期から着手していく
宅建士の合格を決める科目は民法です。
「いやいや、配点が高い宅建業法でしょ」
と考える人もいるでしょう。
宅建業法はたしかに配点が高いですが、暗記要素が強いので、誰がやっても得意科目にすることができます。
不合格者ですら高得点を取ってくるので、合格を決める科目にはなりません。
民法は暗記した知識が得点に直結する科目ではないので、勉強量と結果が比例しません。
継続して学習し、知識が体系的につながったときに得点力がアップする科目です。
民法は苦手とする人が多く、一番差がつく科目です。
そして「理解ができなくて勉強計画が崩れた」となるのが民法です。
いつ得意になるのか読めない科目ですので、早期から着手し、試験本番までに間に合わせるスケジュールを組みましょう。
民法の学習が終われば、宅建士試験の学習は7割終わります。
残りの科目は暗記作業なので、勉強量に比例して得点力があがっていきます。
1カ月以内に合格している(と自称する)短期合格者は、司法試験、司法書士、行政書士などの資格取得者、勉強中の人であることがほとんどで、民法を克服している人たちです。
それだけ、民法は合格を左右する科目なのです。
高配点の宅建業法は民法の次に手をつける
宅建業法は合格を決める科目ではありません。
不合格を決める科目です。
宅建業法で満点or満点-1点を取らなければ、合格は絶望的になります。
しかしながら、問われる論点が限られていて、過去問演習だけでじゅうぶんに満点が狙える科目でもあります。
「〇〇というルールだから」という論点なので、「理解できなくて勉強がすすまない」ということがない科目です。
勉強スケジュールが狂いにくく、学習がすすめやすい科目です。
「配点が高いから、一番最初に手をつけるべきでは?」と思われるかもしれません。
配点が高いからといって学習の初期から手を出してしまうと、民法が間に合わなくなるリスクがあがります。
民法→宅建業法という順番を守ることで、民法の学習が間に合わなくなるリスクを最小限にしつつ、高配点の宅建業法をクリアしていきます。
法令上の制限は、用途制限の暗記から着手する
法令上の制限は、用途制限の暗記ができるかどうかが得点力につながります。
用途制限を暗記できれば、法令上の制限の勉強は5割終わったといえます。
まずは用途制限の暗記作業にとりかかり、暗唱できるレベルまで落とし込みます。
その他、5点免除
5点免除の問題は勉強して得点する必要はありません。
基本的に捨てていきますが、常識で解ける問題が出題されることがありますので、出たとこ勝負で試験に臨みます。
統計問題は知っているところが出題されれば解けるので、試験前日に国土交通省のホームページを印刷して試験会場に持ち込みます。
試験開始5分前まで、着工数などに注目してヤマを貼ります。
試験開始直後に統計問題を解き、ヤマが当たればラッキー、外れれば予定どおり捨てます。
土地、建物に関する問題は常識で解ける問題が多いため、直前期まで放置しても学習が間に合います。
まとめ
配点が高いからといって宅建業法からとりかかってはいけません。
民法を克服した人は、宅建士試験の勉強は7割終わっています。
民法以外は暗記要素が強くなるので、勉強計画も崩れにくく、努力量に比例して得点力がどんどんアップしていきます。
学習スケジュールの次は、学習計画の立てかたもチェック

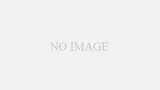
コメント